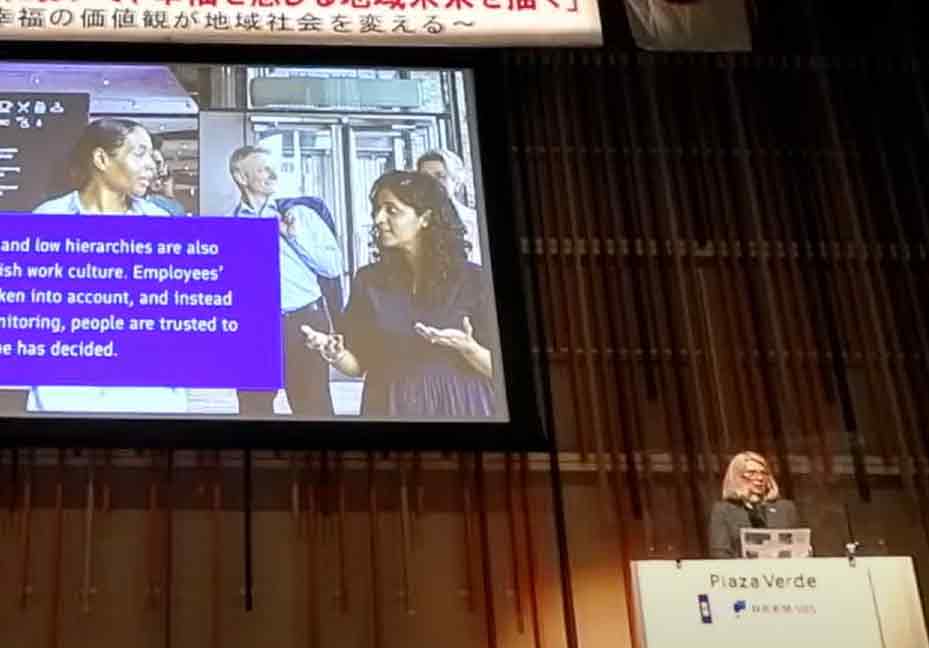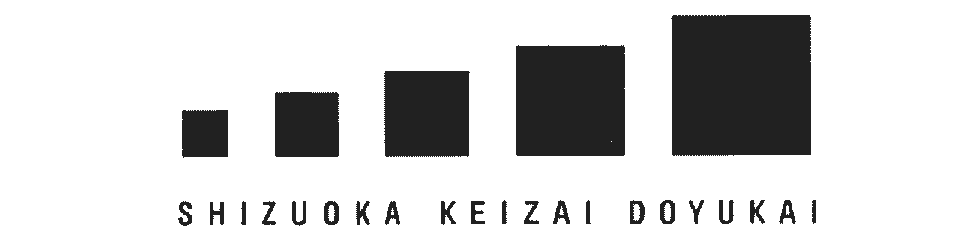2025年1月 公開セミナー
人口減少時代に。
新たな東部の広域連携を目指して
■日時/令和7年1月22日(水) ■場所/プラサヴェルデl 階コンベンションホールA-l
これからの日本は、超高齢化社会に移行し急激な人口減少を迎える時代になります。東部全体の経済が成長し、持続可能で豊かな地域社会を創出して行くためには、東部全体の戦略が必要と考えます。中核市にも満たない各自治体とその町の経済界が行政区域の枠を超え「広域連携」することにより、東部全体の防災・医療・福祉・教育・観光・商業・交通道路インフラ等を豊かなものに躍進させます。または、風光明媚な土地柄で首都圏へのアクセスの良さを利用して、二地域居住の創出・拡大を目指します。そして行政の壁を越えて地域の人々と、多様に関わる新たなイノベーションを生み出すことで関係人口が増え、東部全体のウェルビーイングを加速し充実させて行きたいと思います。
第1部 基調講演
『地域活性化のための「共創」の意識と実践』
事業構想大学院大学 事業構想研究所
社会構想大学院大学 社会構想研究科
産業能率大学 経営学部(兼任教員)教授

河村 昌美 氏
講師の河村教授は、日本全体の人口減少と地域経済の衰退が進む中、これまでの方法では対応できないと指摘した。特に静岡東部地域の課題として、以下の点が挙げられた。
- 人口減少と高齢化の加速:働き手の減少により地域経済の縮小が避けられない。
- 自治体間の連携不足:自治体ごとの施策がバラバラであり、効率的な地域運営が難しい。
- 地域経済の停滞:産業の新陳代謝が進まず、地域経済が活性化しにくい。
これらの課題を解決するためには、行政・企業・市民が協力し、新しい価値を生み出す「競争(共創)」の考え方が必要であると述べた。特に、自治体や企業が独立して施策を進めるのではなく、協力しながら新しいビジネスモデルを構築することが、持続可能な地域づくりに不可欠だと強調された。
成功事例の紹介
- 愛知県豊田市の「介護予防プログラム」
- 民間企業が提供する健康増進サービスを活用し、高齢者の介護リスクを低減するプログラムを導入。
- 参加者の健康データを収集し、一定の成果が認められた場合に行政から成果報酬を支払う制度を設けた。
- これにより、介護費用の削減と地域経済の活性化を同時に実現。
- 横浜市の「広域自治体連携」
- 横浜市と周辺自治体が連携し、技術職員の人材共有、インフラ維持管理の共同実施、行政サービスの効率化を進めている。
- 例えば、65歳以上の専門技術者を再雇用し、複数の自治体で活用する仕組みを導入。
- また、観光施策では、複数の自治体が共同で観光プロモーションを行い、訪日客の流入を促進。
- 日域居住(二地域居住)促進策
- 都市部の住民が地方と都市の二拠点生活を送る「二地域居住」が注目されており、これを支援する施策を展開。
- 静岡県東部は首都圏からのアクセスが良く、自然環境にも恵まれているため、二地域居住の受け入れ地域として大きな可能性を持つ。
- 自治体間で連携し、住まい・仕事・コミュニティ形成の支援を行うことが今後の課題。
地域ブランドとブランディングの重要性
地域活性化のためには、地域ブランドの確立とその発信が不可欠である。静岡東部地域には、沼津の海産物や伊豆の観光地といった特色があるが、それらを単体で発信するのではなく、「静岡東部エリア全体」としてのブランド価値を高めることが重要であると指摘された。
- 自治体単位のPRではなく、広域ブランドとして発信
- 「静岡東部」としてのブランド力を高めることで、国内外の観光客・移住希望者に訴求力を持たせる。
- 地域の特産品や観光資源を組み合わせたプロモーションを実施。
- マーケティングとブランディングの違い
- マーケティングは、供給側(企業・行政)の視点で価値を発信する手法。
- ブランディングは、受け手(消費者・移住希望者)がどのように地域を認識するかに関わるものであり、住民の意識改革も必要。
まとめと今後の展望
本セミナーでは、静岡東部地域が持つポテンシャルを最大限に活かすために、「競争(共創)」の考え方をもとに、行政・企業・市民が連携して取り組むべき方向性が示された。特に、次の点が重要であるとされた。
- 自治体間の連携強化
- 施設の共同利用、観光プロモーションの統一、技術者のシェアリングなど、無駄を省きながら効率的な行政運営を実現。
- 新しいビジネスモデルの創出
- 公共サービスを民間企業と協力して提供し、税金負担を軽減しながら持続可能な地域経済を築く。
- 移住・二地域居住の促進
- 静岡東部の自然環境・アクセスの良さを活かし、首都圏の住民をターゲットにした移住施策を展開。
- 地域ブランディングの強化
- 静岡東部を一つのブランドとして確立し、広域的な視点で魅力を発信。
講演の最後には、「リフレーミング(物事の見方を変える)」と「アップデート(施策の継続的改善)」が重要であると強調された。従来のやり方に固執せず、柔軟に変化を受け入れながら、新しい地域のあり方を模索することが成功の鍵となる。今後、行政と企業が連携しながら、静岡東部地域の可能性を最大限に引き出していくことが期待される。

第2部 パネルディスカッション
『2地域居住時代・到来-行政境を超えて活躍するヨソモノを共有せよ!』

森田 創 氏
合同会社うさぎ企画代表社員・作家、静岡経済同友会東部協議会 会員

日下 雄介氏
国土交通省国土政策局地方政策課課長

中島 あきこ氏
一般社団法人ママとね代表理事、あひる図書館館長、医師・医学博士

河村 昌美 氏
本パネルディスカッションでは、静岡県東部地域の活性化と「2地域居住」について議論が行われた。コーディネーターの森田氏が、地域の魅力や課題を共有し、パネリストとして国土交通省の日下雄介氏、一般社団法人ママとねの中島あきこ氏、経済・地域活性の専門家である河村昌美氏がそれぞれの視点から発言した。
森田氏は、静岡県東部は東京から1時間以内でアクセス可能であり、豊かな自然と食文化があるにも関わらず、地域住民がその価値を十分に理解していないと指摘。地域が外部の人材に選ばれるためには「よそ者の視点」が必要であり、才能をシェアしながら地域を活性化すべきだと述べた。
日下氏は、国として「2地域居住」を推進しており、新法を施行することで、複数の拠点を持ちつつ地域に関わる人々を支援する制度が整えられていると紹介。これにより、地方の課題解決に向けた新たな人材流入が期待されると述べた。
中島氏は、自身の移住経験を踏まえ、静岡東部は新たな移住者や関係人口に対して寛容な地域であるとしつつ、情報発信や子育て環境の改善が必要と指摘。女性が働きやすい環境づくりが地域選びの重要な要素になると強調した。
河村氏は、地域ブランディングの必要性を訴え、地元住民が地域の良さを認識し、外部に発信することが重要と指摘。行政と民間の協力が不可欠であり、既存の制度をうまく活用しながら地域の活性化を図るべきだと提案した。
また、行政と民間の協力のあり方として、「地域生活圏」の概念が紹介され、自治体同士が連携しながら広域でサービスを提供する必要性が議論された。さらに、成功事例として、他地域での空き家再生や都市近郊地域の発展の例が挙げられ、それらの要素を静岡東部にも応用できるのではないかという意見もあった。
最後に、今後の展望として、「2地域居住」の可能性を最大限に活かすために、行政と民間が連携し、地域の魅力を再認識しながら外部に発信する必要性が強調された。


最後に、沼津市長をはじめ、各自治体から感想と提案をいただいて終了しました。
2024年2月 公開セミナー
スポーツと地域 ~どうする県東部~
■日時/令和6年2月7日(水) ■場所/プラサヴェルデl 階コンベンションホールA-l

スポーツによる社会開発
参議院議員 橋本 聖子氏
健康というのは心と体の両方が健康でなければ言えません。成長に関しては右肩上がりの成長を遂げていくという時代は終わったと思います。どれだけ持続可能な社会を築いていくかという成長でなければいけない、そして繋がりだと思います。
スポーツ研究所を文科省の力によって、 国の力によってスポーツ界が非常に効果を上げてきました。健康寿命が延伸される地域や静岡はスポーツ圏であり、素晴らしい観光立国でありますので、スポーツと観光と食、こういったことを結び合わせて、医療がついて、そして付加価値をつけた新しい健康産業というものを生み出していただきたい。
そのことをスポーツ政策の中で一生懸命に実現をする、地域と自治体と連携をして頑張ってやっていきたいと思いますので、ぜひこれからもご指導賜りたく思っております。

身近なスポーツが地域を支える〜世界と日本の違い〜
元NHK アナウンサー法政大学教授 山本 浩氏
スポーツをやっていて悔しいというのはどこから来たのか。その要件はなんだったのか。
他と比較をしたのか、自分の過去を振り返ったのか、これから先どんな目標設定ができるのか。こういうことを実際に分析した上で初めて、この悔しさみたいなものは次のステップになっていきます。
選抜の際にその方法をしっかり知らしめていることは非常に有意義です。
負けて悔しいという怒りのエネルギーを次なるパフォーマンスに転嫁できるのかどうか。 地域への期待というのは、 多様性の発揮の場であることや失敗に対する寛容な精神を育むことであります。選抜に終始しない受け止め方で何よりもかけがえのない空間であることが望ましいでしょう。そして市場を拡大していく、スポーツというのはどの分野にも邪魔をしないものだと思いますので、こういったことの視点で考えていただければありがたいなと思います。
スペシャルディスカッション
「スポーツと地域〜どうする県東部!〜」
⃝パネリスト
山本 浩氏
鈴木 康友氏(元プロ野球選手.独立リーグ監督)
良知 正浩氏(焼津CITYユナイテッド代表)
川瀬 一隆氏(静岡経済同友会東部協議会代表幹事)
⃝司会進行
NHK静岡放送局 大窪 愛キャスター

川瀬代表
コミュニケーションは非常に大事で、例えば 野球観戦やサッカー観戦に行きまして、横に全然違う方が座っていても試合が終わったら同じ応援チーム同士で親しくなる。
今日もわずかこの短時間の中で、皆さんと話をしながら、新しい気づきというのは生まれてきました。今後も皆さんとコミュニケーションを広く繋いでいきたいです。すぐにこの地域との連携とまではいかなくても 応援する力を使って点と点を広げて整備しながら、東部地域の 魅力の中にスポーツっていうもの是非入れていきながら応援していきたいと思います。
2023年2月公開セミナー
with コロナ社会においで幸福を感じる地域未来を描く
~新たな幸福の価値観が地域社会を変える~
■日時/令和5 年2 月8 日(水) ■場所/プラサヴェルデl 階コンベンションホールA-l & YouTube配信
基調講演
タンヤ・カトリーナ・ヤースケライネン氏(駐日フィンランド全権委任大使)
「幸福度5 年連絞世界1 位の理由」
今年度の静岡県経済同友会東部協議会のテーマ「Withコロナ社会において、幸福を感じる地域社会の未米を描く」において、東部協議会では、幸福という概念や価値観を学ぶため、幸福度5 年辿続•IIt界1 位のフィンランドに1 年間焦点を当て勉強してきた。公開セミナーの碁調講演にて、フィンランド大使館に講師の派遣をお願いしていたところ、特別な計らいで、大使自らにご講演頂く運びとなった。
ヤースケライネン大使は、1967年フィンランド生まれ、1995年フィンランド外務省に入省し、ハンガリー、シリア、英国の駐在。来日直前では、政治局副局長としてフィンランドのNATO 加盟申請に携わった。2022年9 月駐日 フィンランド大使に着任。夫と共に来日、3 人の子の母でもある。
世界幸福度報告とは、世界156か国が国民の幸福度をランク付けされるものである。それぞれの国民に同じ質間で、自分の生活を最高から最悪まで10段階の評価を行う。主観的な質問の回答に、政権への信頼、民主主義の質、人口当たりGDP、健康寿命、社会的支援利用、選択の自由度、社会的寛容度、腐敗のない社会など潜在的要因を参照してスコア化する。フィンランドは、2018年以降5年連続でランキングl位となっている。
世界的繁栄4 位。
国民全てに健康管理と収入保防が約束されている。人口当たりのGDPのみでは幸福度を説明できない。
世界で最も安定している国1 位。
幸福の基盤であるフィンランドの社会は、幸せになるための仕組みが整っている。良い統治は幸福の要である。投禦率、立法府の独立性、議会における女性の議席数では世界で•J11文も優れたガバナンスを持つ国である。政治・社会・経済の団結力も安定している。100年前から政府は党派を超え協力し合い、長年にわたり政治が安定している。世界で被も汚職が少ない国でも評価されている。
制度・公的機関への信頼3 位。
警察への信頼は高く90%以上の支持を得ている。デジタル社会に対する信頼も高い。健康管理のカードは全てデジタル化され医者・患者・薬局が共有しており、医者が変わっても同じ診察を受けることができる。銀行取引もオンラインで行われ、税務局と繋がっており、オンラインでの税務申告し納税が可能で、自宅で子供が寝た後でも手続きができる。
自国民を信頼できる1 位。
国民の85%が自国民を信頼できると同答している。赤ちゃんが外で昼寝し、子どもたちが自分たちで通学できる。公平かつ平等であれば自ずと信頼が得られる。
包容社会2 位。
社会的権利と平等を非常に重視している。障告の有無、性別、出生地による差別はほとんどない。マイノリティに対する包容社会1 位。差別や暴力はほとんどなく、性的マイノリティも広く受け入れられている。
ジェンダー平等2 位。
平等に対する強い取り組みが無ければ世界一にはなれなかった。
母親の働きやすい国3 位。
労働人口の約50%女性である。保育にお金がかからず、出産育児時に権利が守られ、キャリアを継続できるからである。これは100年にわたり女性議員の議席数を確保してきたことが要因のひとつ。
ワークライフバランス1 位。
育児休暇、フレックスタイム、テレワークが允実しており、子育て中の両親以外でも、仕事とプライベートが簡単に両立できる。1 日10時間以上仕事をすると周りから仕事の効率が良くないと思われてしまう。若手の外交官は5週間ホリデーを取得できている。職場でも家庭でも男女平等で80%の男性が育児休暇を取得している。父親が母親より学齢期の子どもと過ごす時間が、先進国の中で最も長い国である。
◆母親になるのに最も適切な国2 位。
出産前の無料ケア、育児休暇1 年間の取得ができ、ネウボラ(産科と小児科の全国ネットワーク)で無料で相談アドバイスが受けられる。全ての赤ちゃんが平等にスタートをきる(生まれた時からの幸せ)。1938年からマタニテイパッケージ(育児用品セット)を配布している。子どもの権利を守り、尊重し、継続的な改善に取り組んでいる。
◆教育へのアクセス1 位
幼稚園から高等教育まで授業料は無料なので、全ての人に大学に通う権利がある。1940年代から学校で温かいランチを提供している。これはジェンダー平等の点からも、母親がランチを作らなくて済むので、母親のキャリアを築くことができる。教育は、学校を卒業しても生涯学習として職場や外部でのスキル向上をサポートしている。
◆きれいな自然1 位
常に身近に自然があり、自然に親しむことで健康を育む。きれいな水、汚染されていない空気、森林などは健康や幸福に大く買献している。将来にわたって自然環境を守るため持続可能な開発を優先している。
まとめに、幸福は一つの要素でできているのではなく、色々な要素でできています。幸福は私たちの心が幸せなのかではなく、社会が私たちを幸せにしている。
パネルディスカッション
「With コロナ社会において、幸福を感じる東部地域の未米を描く」
■ コーディネーター
大野哲廣氏({惟岡経済同友会東部協議会代表幹事)
■パネラー
高野翔氏(福井貼立大学地域経済研究所准教授)
越前市総合計両審議会会長、福井市及び永平寺町のまち・ひと・しごと創生総合戦略有識者委貝
ウェルビーイングの概念を自治体政策活用する研究とウェルビーイングを培進するまちづくり活動を実践。2009-20年J ICA(国際協力機梢)にて、約20 ヶ国のアジア・アフリカ地域で持続可能な国づくり・地域づくりのプロジェクトを担当。2014-17年には、ブータン王国にて、人々の幸せを国是とするGNH (Gross National Happiness) を軸とした国づくりに協力。
中屋香織氏(A Lami Stay le代表ライフスタイルデザイナー)
キャリアアップと家庭の両立を目指したが乳がんを患い、本当に幸せな住まい方を追及。自身のライフスタイルを見直した結果、首都圏から熱海市に移住。13年間携わった不動産業界での知識と移住経験をいかし、今のライフスタイルに違和感を持つ人へ自分らしく暮らす相談とサポートを行う「ライフスタイルデザイナー」として独立。移住・ライフスタイル・住居探しへの相談が後を絶たない。
山形与志樹氏(慶応義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授)
国立環境研究所・地球環境研究センター・主任研究員として地球温暖化対策研究に取り組む。国際学術プログラムの国際オフィス代表、国連気候変動パネル代表執筆者、日本学術会議連携会員(環境)などを20年間歴任。気候変動対策、生態系サービス評価、土地利用ー交通システム、都市の都市持続可能性に関する閑境省やJST等の研究プロジェクトを推進中。
東部地域の未来を「幸福」という切り口で、パネラーそれぞれの視点で、ウェルピーイング、生活スタイル、社会インフラなど多彩な意見が交換され、非常に参考になる充実したパネルディスカッションとなった。